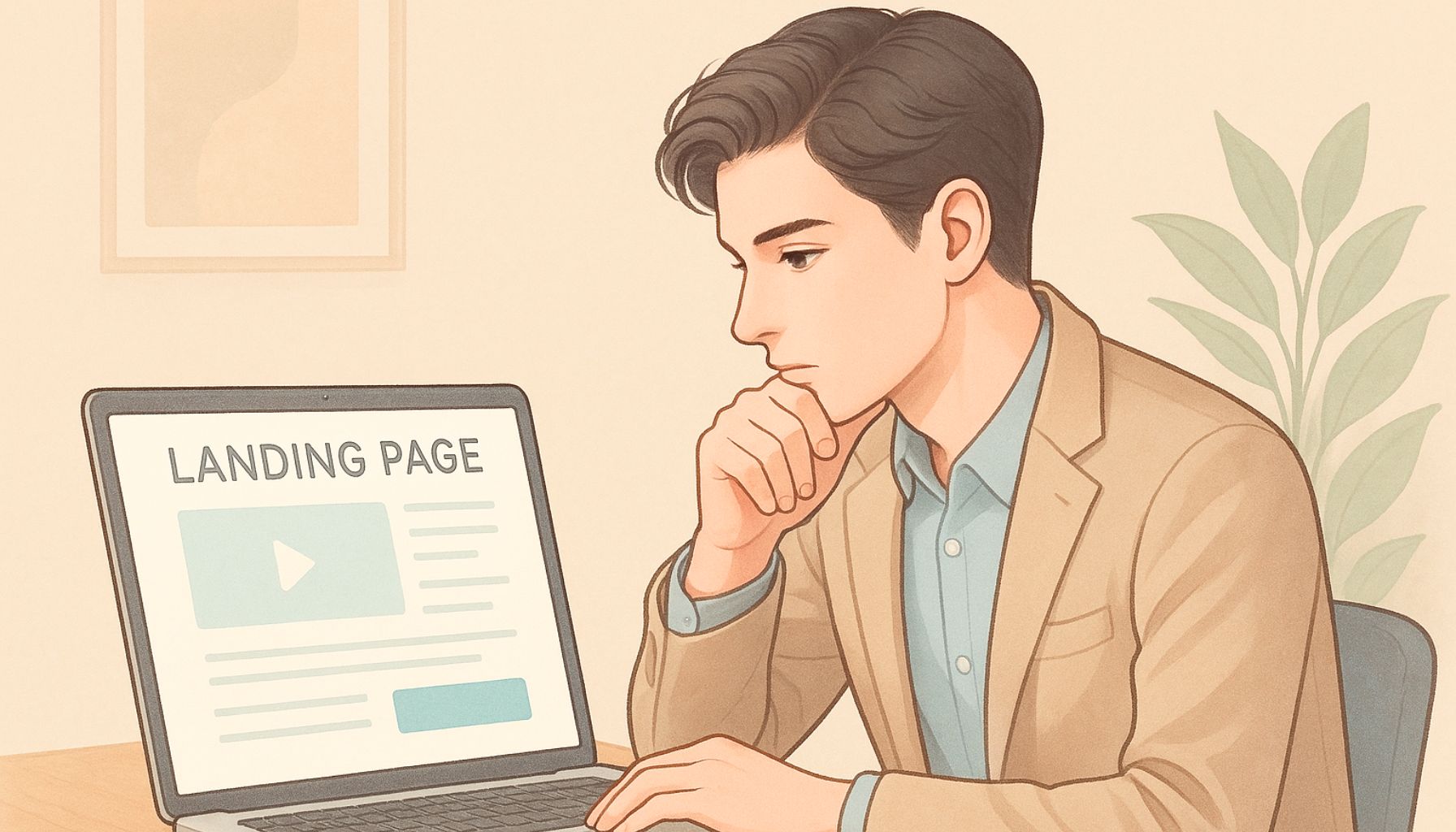法人向け会員サービスの展開方法:企業向けプランの作り方

会員制ビジネスが個人向けから法人向けへと広がる中、安定した収益源として「法人プラン」を導入する企業が増えています。これから有料会員サービスに取り組む事業者にとって、法人契約はLTVを高めるチャンスでもあります。この記事では、法人向け会員プランの設計・導入の具体的な方法と、事業に取り入れる際の実務的なポイントを詳しく解説します。
なぜ今、法人向けの会員プランが注目されているのか?
従来、会員制といえば個人ユーザーが中心でしたが、最近は法人ユーザー向けのサブスクリプション型ビジネスが急増しています。背景には以下のような理由があります。
- 働き方の多様化により、リモート研修やクラウド型サービスの導入が進んでいる
- 経費計上が可能なため、法人側の導入ハードルが低い
- 月額・年額の継続契約によって売上の予測が立てやすくなる
特にSaaSやオンライン教育、業務支援ツールを提供している企業にとっては、法人契約はスケーラビリティの高い成長戦略です。
さらに、法人契約は単なる売上増にとどまらず、「継続的な関係構築」「サービス改善に向けたフィードバックの獲得」「ブランド信頼の強化」といった副次的効果も大きく、企業全体の成長を後押しする仕組みとして注目されています。
法人プラン導入のメリットと向いているビジネスとは?
法人向け会員プランには、以下のようなメリットがあります。
- 月額課金でも人数×契約により単価が高い
- 一度契約すると長期利用が多く、解約率が低い
- 決済や担当者対応などが明確で、運営が安定しやすい
特に法人は一度サービスに満足すれば、長期間にわたり利用を続けてくれる傾向が強く、解約の心理的・制度的ハードルも高いため、安定的な収益源として非常に魅力的です。
単価も継続率も高いって、法人ってほんとありがたい存在だよね〜

法人契約に向いているサービスの特徴
- 社員の育成や業務効率に直結する(例:eラーニング、勤怠管理)
- 1アカウントで複数人利用が見込める(例:ライセンス販売、ツール利用)
- データ管理・セキュリティに配慮されている(例:顧客管理、プロジェクト管理)
特に「従業員全体で使える汎用性の高いサービス」や「成果が数値で見えやすいツール」は法人に好まれる傾向にあります。また、福利厚生として活用できるサービスも、採用・定着率アップを狙う企業にとって魅力的な導入理由になります。
導入前に確認すべきポイント
- 法人契約に関する請求・契約フローは整っているか?
- サポート体制(専任担当・電話対応など)は確保できるか?
- 導入後の継続利用の仕組み(カスタマーサクセス設計)があるか?
これらの基盤が整っていないまま法人営業をスタートすると、問い合わせ対応や契約後のトラブル対応に追われてしまい、本来の事業成長にブレーキがかかってしまうケースもあるため注意が必要です。
法人向けプラン設計の基本ステップ
法人契約は個人契約とは異なる設計が求められます。以下のステップを意識しましょう。
設計ミスると後が大変だから、準備は“じっくり確実”がポイントだよ

ステップ1:対象法人のニーズを徹底リサーチ
「どんな業種」「どんな課題」を持った法人がターゲットになるのかを明確にします。業種別に異なるニーズを理解し、法人ユーザーに刺さるプラン設計につなげます。
業界ごとに抱える課題は異なるため、法人向けプランでは「横展開できる要素」と「業種特化の要素」をバランスよく織り込むことが重要です。たとえば、IT業界であれば導入スピードとAPI連携、教育業界であれば成績評価レポートや一括管理機能などが重視されます。
ステップ2:料金体系・利用人数の設計方法
法人向けは「人数単位」や「部署単位」で料金が発生するモデルが多いです。例として:
- 5名まで月額〇〇円、それ以上は1人追加ごとに〇〇円
- ライトプラン/スタンダードプラン/エンタープライズプラン など段階的に設定
加えて、年契約割引や管理者向けダッシュボード付きのプレミアムプランを用意すると、大企業にも刺さる価格設計が可能です。複数名契約が前提となるため、1ユーザーあたりの単価が下がっても、全体売上は大きくなる傾向があります。
ステップ3:法人ならではの提供価値を設計
個人向けとの差別化を図るために、法人プラン限定の特典や機能を用意します。
- 複数ユーザー管理機能(管理者設定・アクセス制限)
- 利用レポート・分析ダッシュボードの提供
- 契約書発行、個別対応などの法人向けオプション
また、導入企業専用のSlackチャンネルやオンボーディングサポートなど、「他社と違う体験ができる」工夫を盛り込むことで、価格以上の価値を感じてもらいやすくなります。
ステップ4:契約・請求・サポート体制の整備
法人契約は請求書払い、年間契約、稟議対応などが必要な場合もあるため、
- 請求書・領収書発行の自動化
- 年額一括払いへの対応
- 法人営業用の導入資料や見積テンプレートの用意
など、営業・経理・サポートの連携が重要になります。
さらに、IT系であればISMSやPマークなど、情報管理体制に関する説明資料の整備も信頼獲得の鍵となります。営業現場から「書面が欲しい」と言われたときに即座に対応できる準備があると、受注率は確実に向上します。
法人が魅力を感じる3つのポイントとは?
法人向けプランを設計するうえで、契約者が重視するポイントを押さえておくことが大切です。
カスタマイズ可能な機能やサポート体制
自社の運用に合わせて柔軟に使える設計、そして導入時やトラブル時に相談できる「安心感」が法人契約では重要視されます。
たとえば、特定の部署だけアクセスを制限したい、管理者権限を細かく設定したいといったニーズに応えられる機能を用意することで、提案の幅が広がります。カスタマーサクセス担当の設置や、導入時の初期設定代行も喜ばれる要素です。
複数人利用や管理者権限など“業務効率”視点の価値
管理者が社員のアカウントを一括管理できたり、利用状況の把握ができる機能は、業務効率化の視点から高く評価されます。
特に人事や総務部門の業務を軽減できる仕組みは、導入の決め手になりやすいため、業務フローへの影響を具体的に伝えられる提案資料が効果を発揮します。
導入実績やセキュリティの信頼感
他社導入事例や、個人情報保護・データセキュリティに関する説明があることで、「安心して導入できる」と判断されやすくなります。
「導入企業数」「業界別の利用例」「定着率や効果測定データ」など、数値を交えた情報があると説得力が増します。また、ISO27001などの認証を取得している場合は積極的に開示しましょう。
安心・便利・実績!法人はこの3つで心をつかめばOK!

よくある法人向けプランの料金モデルと設計例
料金体系も法人向けでは少し工夫が必要です。代表的なモデルは以下の通りです。
- 月額×人数課金モデル(5名まで基本料金+1名ごとに追加課金)
- 段階式モデル(例:〜10名〇〇円/〜50名〇〇円)
- 年間契約割引型(12か月契約で1か月分無料など)
また、導入ハードルを下げるために「30日間無料」「導入サポート付き」などのオファーも有効です。営業資料には料金表だけでなく、導入の流れ・効果・FAQをセットにすると信頼性が高まります。
料金プランって意外と奥が深い。わかりやすさと柔軟性がキモだね

法人営業・販売の進め方と導線設計
法人向けプランを作っても、導線が整っていなければ契約にはつながりません。以下のような流れを整備しましょう。
問い合わせ・資料請求ページの整備
Webサイトに法人向けの「よくある質問」「導入メリット」「プランの違い」を明示したページを作り、そこから資料請求・相談予約につなげます。
オンライン商談・ヒアリングの実施
事前アンケートやヒアリングシートを活用して、相手の課題を可視化し、最適なプランを提案できるようにします。必要であればデモンストレーションも行いましょう。
MAツールやインサイドセールスの活用
問い合わせのあった法人に対して、ステップメールやホワイトペーパーを使って継続的にアプローチ。営業の属人化を避けながら効率的に案件化を進めます。
作って満足じゃダメ!売れる流れもちゃんと組み立てないとね

導入事例と活用パターン(成功事例3選)
IT系サービス(SaaS)
あるSaaS企業では、チームごとのログイン管理機能を法人プランで提供し、大手企業への導入に成功。導入後はカスタマーサクセス担当がフォローし、解約率を大幅に下げています。
教育・研修系プログラム
eラーニングサービスでは、企業研修用の「受講履歴レポート」機能を加えることで、法人契約の獲得数が3倍に増加。人事担当者に好評でした。
サブスク商品の法人導入
健康食品や文房具などを扱う企業では、福利厚生の一環として法人プランを導入。総務部からの一括申し込みで、継続的な売上を得られるモデルに成長しました。
他社の成功例は宝の山!“どう応用できるか”を考えるのがコツだよ

まとめ|法人向けプランは“特別感”と“信頼性”がカギ
法人向け会員サービスは、「売上の安定化」「顧客との関係深化」という点で非常に有効なモデルです。個人向けと同じ設計では成果が出にくいため、法人特有のニーズに寄り添った構築が求められます。
特別感・カスタマイズ性・サポート力・導入実績といった“信頼性”の演出が、法人の意思決定を後押しします。まずはスモールスタートで小規模法人から始め、少しずつアップグレードしていく姿勢が成功の鍵です。